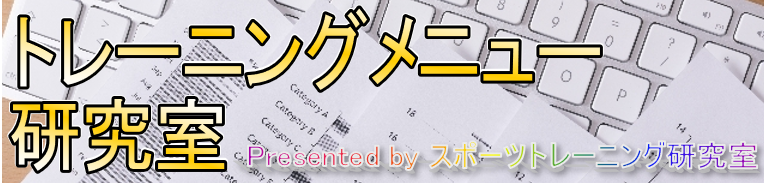近年の部活動やサークルなどのアマチュアチームでは、専門的な知識を持った指導者はいないことが多いのが現状です。現在のトレーニング方法が本当に正しいのか疑問を抱きながらも、貴重な時間を費やしてよいのでしょうか。
練習メニューとトレーニング環境を作成する
 「競技が上達したい」のなら、自身のトレーニング環境を分析し、可能性を最大限引き出しましょう。
「競技が上達したい」のなら、自身のトレーニング環境を分析し、可能性を最大限引き出しましょう。
環境の整ったクラブチームへの参加が理想的ですが、申込時期やセレクション(入門試験)に受かるとは限りません。
また入ったクラブチームが必ずしも適切な環境とは限らず、評判とは異なることも少なくありません。
理想的な練習やトレーニング環境をすぐに作成できる保証はありませんが、その過程で多くを学ぶことでしょう。
正しいトレーニング効果がスポーツパフォーマンスを上げるコツ
私は予防介護やジムトレーナーとして学習する中で、多くの誤解に気づきました。最新の研究まで深く学ぶ必要はありませんが、情報が容易に手に入る現代において、効果的で効率的なトレーニングメニューの作成は、時間と努力次第で可能です。
現在では多数の書籍が販売されており、Amazonや楽天などで手頃な価格の中古本も入手可能です。それらを数冊読むだけでも、トレーニングメニューに大きな変化が生まれることでしょう。
焦る気持ちを抑え、正しい順序で学習を進めることが大切です。
トレーニングの基礎から始める
いきなり特定の分野に特化した内容ではなく、まずはトレーニングの基本的な書籍がおすすめ。
経験則だけでは、間違った指導者と同じ道を歩むだけ。勉強を始めれば経験則で正しいと思っていた今までの練習メニューが実は誤りであったり、非効率だったかを実感することになるでしょう。
▶ トレーニングの基礎とは
トレーニング要素と各分野への発展
 紹介するトレーニングの基礎関連の本を読んだら、ご自身の気になる分野の本を読んでみましょう。イマイチしっくり来ない方は、当サイト上部から別カテゴリーを読んでみましょう。
紹介するトレーニングの基礎関連の本を読んだら、ご自身の気になる分野の本を読んでみましょう。イマイチしっくり来ない方は、当サイト上部から別カテゴリーを読んでみましょう。
例えば栄養関連のサイトを紹介します。
- 競技練習
適切なレベルの練習メニューを設定し、少し上のレベルにも挑戦する。 - 筋トレ
全身のバランスを考慮し、セット数やレップ数を調整する。
▶筋トレの始め方 - フィジカルトレーニング
姿勢や競技特性を理解し、年齢に応じたトレーニングを優先する。
▶フィジカルトレーニング研究室 - 回復(休息)と栄養管理
部活中にも栄養補給ができる人は行う。
▶スポーツの栄養管理の基礎とは - コンディショニング(体調管理)
時間が空いた人はストレッチでも良い。
▶スポーツのコンディショニングの基礎とは - 本やスマホから要素を積極的に取り入れる
・積極的に本やスマホで見本動画を取り入れましょう。
・動画を撮れる場合は自分の動きを確認し、イメージと実際の動きをすり合わせましょう。
▶コーディネーション
・人数調整の時間を見本動画や自身の動き、自身の課題と目標の確認に活用しましょう。
スマホがあれば体調管理を記録し、自己分析ができる!
ご自身の体調(コンディション)をスマホに記録し、分析することも重要。
スマホを中心に、体組成計、スマートウォッチ、スマートリングなどを徹底活用することで、一昔前に超一流プロアスリートしか出来なかった体調の管理法(コンディショニング)が今は誰でも出来ます。
段階を踏みながら個人のトレーニング環境を作成する
部活やチーム練習、トレーニングとは別に、個人でのトレーニング環境を作成します。
当サイト前半で説明したピリオダイゼーション(期分け)を意識し、無理な計画でオーバーワークにならない様に段階を踏めばOK!
▶いつも疲れていることが正しいトレーニング!?「オーバーワーク症候群」とは
【練習メニューとトレーニング要素を分析する】
- 最初からチームを動かすことは難しいので、まずはチームの練習メニューを毎日記録し、筋トレ、アジリティトレーニング、栄養管理など可能な限り要素を分類します。
▶ボディデザイン講座の「レコーディング法」とは - 記録から貴方のスポーツにとって足りない要素から追加することを目指します。
【分析したトレーニング要素から補強メニューを作成する】
- 簡単に習慣化できることから始める。
体力的に余裕がなければ、スマホで動画を見て上手い人を分析したり、可能であれば自分のプレイ動画を撮影し、上手い人との差を分析する。
▶自分の理想と実際の体の動きの差「コーディネーション」とは - 体組成計とスマホを連動させ、毎日の記録をとる。
▶体調管理を記録するレコーディング法と実践法とは - 例えば栄養管理や回復(休養)では、早寝、早起き、朝食を食べる。次に間食を増やす。
お風呂に入った後にストレッチやマッサージを行う。
▶回復力を高める半身浴とは
【自宅に筋トレ環境を作成する】
- 部活やクラブなどチームのトレーニングが足りなかったり、余裕が生まれてきた場合。
自分のプレイ動画の分析から「筋トレが足りない」と判断した場合は、個人で補強トレーニングのメニューを作成する。
▶競技で足りない筋力を補う「補強トレーニング」とは - 無理のない範囲で自宅に筋トレ環境を作成してみましょう。
お金を掛けるのではなく、最小限の工夫が最適だったりします。
とりあえずトレーニングチューブさえあれば大抵のことは充分。
▶自宅に筋トレ環境を作る
個人に必要なスポーツトレーニングを上で簡単に内容を上げましたが、細かい実践的な内容はボディデザイン講座にまとめてあります。
体調の管理管理法がスポーツのパフォーマンスに与える影響は大きく、読めば納得してもらえると思います。
▶スポーツアスリートにも共通する体調の管理法は「ボディデザイン講座」